
不動産クラウドファンディングを基本に、投資についてのお話
お金と資産形成について、休憩時間や通勤時間の暇つぶしになってタメになるコラム
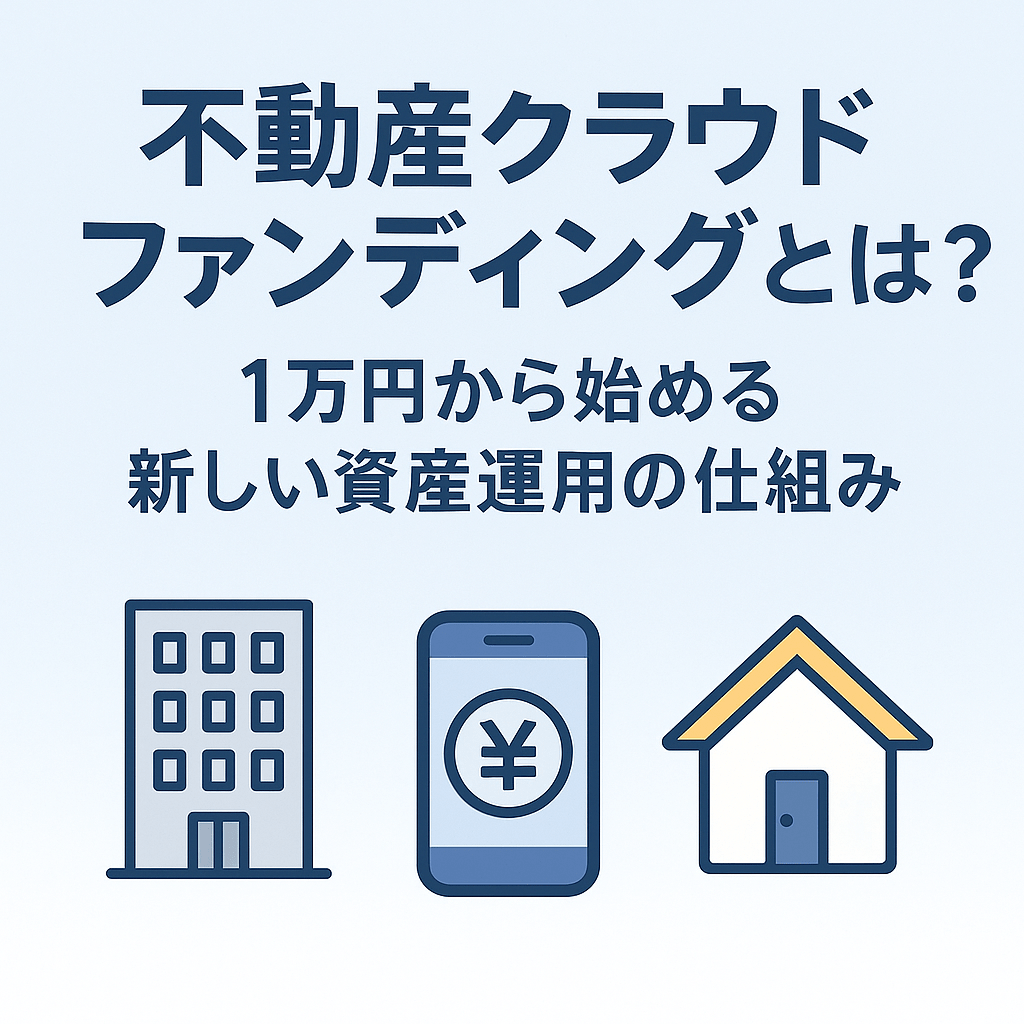
最近、ニュースやSNSでも目にする機会が増えてきた不動産クラウドファンディング。「なんとなく不動産投資っぽいけど、普通の不動産投資と何が違うの?」と感じている人も多いのではないでしょうか。
実は、不動産クラウドファンディングとは、インターネットを通じて、少額から不動産に投資できる新しい資産運用の仕組みのこと。
不動産を一人で購入する必要がなく、複数の投資家が少しずつ資金を出し合うことで、賃料収入や売却益などの不動産収益を分配で受け取れる仕組みです。
近年では、低金利や物価上昇(インフレ)の影響で「銀行に預けてもお金が増えない」と感じる人が増え、安定した収益を得られる“実物資産型投資”として注目が高まっています。
本記事では、不動産クラウドファンディングの
をわかりやすく解説します。
読み終えるころには、「自分にこの投資が合っているか」がきっと明確になるはずです。
不動産クラウドファンディングとは、インターネットを通じて少額から不動産に投資できる新しい資産運用の仕組みです。従来の不動産投資では、数百万円〜数千万円といった大きな資金が必要でしたが、クラウドファンディング型の不動産投資なら、1万円程度の少額から始めることが可能です。
この仕組みは、国が定める「不動産特定共同事業法(不特法)」に基づいて運営されており、各社が登録事業者としてファンドを募集・運用しています。そのため、法律に則った透明性の高い形で不動産投資に参加できる点も特徴です。
不動産クラウドファンディングの最大の特徴は、1人では購入できない不動産を複数の投資家が共同で出資・所有する点にあります。
例えば、マンションの1室を運用して家賃収入を得る場合、投資家は物件を直接管理する必要はなく、運用期間が終わると配当金と元本が自動的に戻ってきます。つまり、「実物資産への投資」×「インターネットの手軽さ」を融合させた新しいスタイルの投資と言えます。
不動産クラウドファンディングが急速に注目を集めている背景には、法律改正と時代の変化があります。
まず、2017年の「不動産特定共同事業法(不特法)」の改正により、オンライン上で不動産投資を募集・運用できるようになりました。これにより、これまで法人や富裕層しか参入できなかった不動産投資が、一般の個人でも簡単に参加できる時代になったのです。
さらに、低金利が続く日本では、銀行にお金を預けてもほとんど増えない現状があります。
加えて物価上昇(インフレ)の影響もあり、「資産を守りながら増やす」ための選択肢として、安定収益を狙える不動産クラウドファンディングが注目されています。
また、株式やFXのように日々の価格変動に一喜一憂する必要がなく、安定した家賃収入ベースで運用できる点も投資初心者に人気の理由です。
不動産クラウドファンディングは、従来の不動産投資を「インターネット上で小口化」した仕組みです。運営会社が選定した物件を「ファンド」として公開し、投資家が少額で出資します。出資された資金で物件を運用し、賃料収入や売却益を原資に配当を行うという流れが基本です。
投資家は物件の管理や契約、入居者対応などを自分で行う必要がなく、手軽に不動産収益を得られる点が大きな特徴です。つまり、“不動産の安定性”と“クラウドの手軽さ”を組み合わせた投資方法と言えるでしょう。
不動産クラウドファンディングの運用は、以下のようなシンプルなステップで進みます。
このように、投資家は出資後の運用をすべて運営会社に任せられるため、「不動産投資の手間」を大幅に省ける点が魅力です。また、サイト上で運用レポートや分配実績が公開されるため、透明性の高い運用状況を確認できます。
不動産クラウドファンディングでは、投資家を守るために「優先劣後(ゆうせんれつご)構造」という仕組みが導入されています。
投資家は「優先出資者」、運営会社(事業者)は「劣後出資者」として資金を出します。このとき、万が一物件の価値が下がったり、予期せぬ損失が発生した場合、劣後出資者である運営会社が先に損失を負担します。
たとえば、物件が10%値下がりしても、運営会社がその10%分を負担すれば、投資家は元本を守れるケースもあります。このように「運営会社が自らもリスクを取る」構造によって、投資家の安全性が高められているのです。
ただし、劣後出資割合(例:10%〜30%)はファンドごとに異なるため、投資前に必ず募集ページで確認することが大切です。
実際に多くの不動産クラウドファンディング事業者がこの仕組みを活用しています。中でも「トモタク」は、1口1万円から始められる少額投資型の不動産クラウドファンディングとして人気です。
各ファンドページでは、
といった情報がすべて公開されており、投資家が安心して判断できるようになっています。
また、会員登録から出資・配当受け取りまでがすべてオンラインで完結するため、初心者でも手軽にスタート可能です。スマートフォン1つで始められる利便性と、透明性の高い運用体制が支持され、利用者が増加しています。
不動産クラウドファンディングの魅力は、従来の不動産投資では難しかった「少額・手軽・安定」を実現している点にあります。高額な頭金やローン契約、物件管理の手間をかけずに、不動産の収益を享受できる新しい投資スタイルとして人気が高まっています。
ここでは、代表的な5つのメリットを順に見ていきましょう。
不動産クラウドファンディングの最大の魅力は、少額から不動産投資を始められることです。
通常の不動産投資では、物件の購入費や諸費用を含めて数百万円〜数千万円の資金が必要ですが、クラウドファンディング型では1口1万円から投資が可能です。まとまった資金を準備しなくても、不動産の収益構造(家賃収入・売却益など)に参加できるため、「将来に向けて資産運用を始めたい」「リスクを抑えて少しずつ投資したい」という初心者に最適です。
少額からスタートできるため、まずは体験感覚で1案件に出資し、仕組みを理解しながら投資を広げていくこともできます。
通常の不動産投資では、購入後に物件管理・入居者対応・修繕・契約更新など、さまざまな業務が発生します。
しかし、不動産クラウドファンディングでは、それらの煩雑な手続きをすべて事業者が代行します。
投資家は、物件を選び出資した後は、運用レポートや分配金の報告を待つだけの“ほったらかし投資”が可能です。日々の値動きに神経を使う必要もなく、忙しいビジネスパーソンや主婦の方でも手軽に続けられます。
「時間をかけずに資産を増やしたい」「不動産投資に興味はあるけど管理が大変そう」という人にぴったりの投資方法です。
1案件あたりの投資金額が小さいため、複数のファンドに分散投資できるのも大きなメリットです。
地域・物件タイプ・運用期間などを分けて出資することで、特定の案件に依存せずリスクをコントロールできます。
例えば、都心のオフィスビル系ファンドと地方の住宅系ファンドを組み合わせれば、景気変動や需要の偏りに強いポートフォリオを構築できます。株式やFXのように相場が急変するリスクが少なく、安定性と分散性を両立できる投資手法といえるでしょう。
不動産クラウドファンディングでは、「優先劣後出資構造」というリスクを軽減する仕組みが採用されています。
これは、投資家を「優先出資者」、運営会社を「劣後出資者」として、損失が発生した際に運営会社が先に損失を負担する仕組みです。
たとえば、物件が10%値下がりしても、劣後出資割合が20%あれば、投資家の元本は保全される可能性があります。つまり、事業者も自らリスクを負うことで、投資家と同じ方向を向いて運用しているという安心感が生まれるのです。
最後に、不動産クラウドファンディングは、相場変動の影響を受けにくく、安定した運用が期待できる点も魅力です。
不動産は実物資産であり、価格がゼロになることはほとんどありません。また、家賃収入をベースに配当が支払われるため、長期的に安定したキャッシュフローを得やすい特徴があります。
銀行預金よりも高い利回りを狙え、株式や投資信託のように日々の値動きに左右されにくいです。まさに「リスクを抑えながらコツコツ増やす」タイプの資産運用として、多くの投資家から支持されています。
どんな投資にもリスクはつきものです。
不動産クラウドファンディングも「少額・手軽」に始められるとはいえ、元本が必ず戻る保証はない点を理解しておくことが大切です。
ここでは、投資を検討するうえで知っておきたい主な4つのリスクと注意点を紹介します。仕組みを理解したうえで冷静に判断すれば、無用な損失を防ぎ、より安心して投資を行うことができます。
不動産クラウドファンディングは金融商品取引法や不動産特定共同事業法に基づいて運営されていますが、元本保証の仕組みではありません。運用する物件の稼働状況や市場環境によっては、想定通りの収益が得られなかったり、損失が発生する可能性があります。
たとえば、入居率の低下や不動産価格の下落、災害などによって収益が減少した場合、配当が下がる、あるいは元本割れするリスクもゼロではありません。
また、ファンドの募集ページに記載されている「想定利回り」は、あくまで目安であって確定ではないことも重要なポイントです。リスクを理解したうえで、「余裕資金」での運用を心がけましょう。
不動産クラウドファンディングでは、運用そのものを事業者に任せる仕組みのため、運営会社の信頼性が最も重要です。事業者の運営実績、ファンドの公開情報、物件の選定基準、そして金融ライセンス(例:第二種金融商品取引業、不動産特定共同事業者登録)を確認することが基本です。
信頼できる事業者は、運用レポートの開示やリスク説明を丁寧に行っています。反対に、情報公開が不十分な事業者は避けるべきです。不安な場合は、実績のある事業者から始めてみると安心です。
透明性と安全性を重視した運営会社を選ぶことで、投資リスクを大きく下げることができます。
不動産クラウドファンディングの多くは、運用期間中に中途解約ができない仕組みになっています。
一度出資した資金は、運用終了まで引き出せないため、生活費や急な出費に備える資金とは切り離して投資することが大切です。
たとえば、運用期間が6か月〜12か月のファンドが一般的ですが、その間に資金が必要になっても途中で解約することはできません。したがって、「余剰資金」での投資を徹底し、資金計画を立ててから出資するのが理想です。
また、運用期間や償還スケジュールは各ファンドごとに異なるため、事前に募集ページでしっかり確認しておきましょう。
投資を検討する際に「利回りの高さ」だけに注目するのは危険です。一般的に、高利回り案件には高いリスクが伴う傾向があります。
たとえば、再開発エリアの商業施設や地方の築古物件など、想定利回りが高い案件は、空室リスクや価格変動リスクも大きくなる可能性があります。
一方で、立地が良く需要が安定している物件は利回りが低くても安全性が高い場合が多いです。
利回りの数字だけでなく、立地・物件タイプ・運営会社の姿勢・優先劣後比率などを総合的に判断することが大切です。「リターンの裏には必ずリスクがある」という原則を忘れず、バランスを重視した投資を心がけましょう。
不動産クラウドファンディングは、少額で始められる一方で、事業者や案件選びを間違えるとリスクが高まる可能性もあります。
特に初心者の場合は、「どこで」「どんな案件に」「どのように」投資するかをしっかり理解しておくことが大切です。
ここでは、失敗しないための基本ステップを4つの流れで紹介します。
まず最初のステップは、信頼できる不動産クラウドファンディング事業者を選ぶことです。
不動産クラウドファンディングは「不動産特定共同事業法(不特法)」に基づいて運営されるため、国や自治体の登録を受けた「不動産特定共同事業者」であるかを必ず確認しましょう。
さらに、以下の3つのポイントをチェックするのがおすすめです。
これらを確認することで、安全性の高い事業者を見極めることができます。
次に意識すべきなのが、いきなり大きな金額を投資しないことです。
不動産クラウドファンディングのメリットは、1万円などの少額から参加できる点にあります。その強みを活かして、複数の案件に分散投資するのがリスク管理の基本です。たとえば、運用期間・立地・物件タイプ(マンション・商業施設・ホテルなど)を分けて投資することで、1つの案件でトラブルが起きても、全体のリスクを最小限に抑えられます。
初心者のうちは、「1口1万円×3〜5案件」のように分散させて始めるのが安心です。
出資後も、「投資したら終わり」ではありません。
ファンドによっては、定期的に運用レポートや配当レポートを配信している場合があります。
これらのレポートを通じて、
を知ることで、自然と不動産投資の知識が身についていきます。
実際の運用を“リアル教材”として捉え、「投資しながら学ぶ」意識を持つことで、次の投資判断に活かすことができます。
特に投資初心者には、学びながら安心して始められる事業者を選ぶことが重要です。中でも「トモタク」は、ファンド情報の開示が丁寧で、
も明確に示されています。
さらに、投資の流れやリスク説明をわかりやすくまとめたコンテンツも充実しており、初心者が理解しながら安心して投資を始められる環境が整っています。
「知識ゼロから始めたい」「安全性を重視したい」という方は、こうした教育的サポートのある事業者を選ぶのがベストです。
不動産クラウドファンディングは、これまでの「不動産投資=高額・難しい」という常識を大きく変えた、新しい資産運用の形です。
インターネットを通じて1万円からでも不動産に投資できる仕組みは、投資初心者にとっても非常に魅力的な選択肢と言えるでしょう。
もちろん、元本保証ではないためリスクは存在しますが、仕組みを正しく理解し、信頼できる事業者を選ぶことでリスクを最小限に抑えながら安定した収益を狙うことが可能です。不動産クラウドファンディングは、株式や投資信託のように市場の値動きに左右されにくく、長期的な資産形成にも向いています。
「資産運用を始めたいけれど、何から手をつければいいかわからない」そんな方にこそ、不動産クラウドファンディングはおすすめです。
少額から始めて経験を積みながら、不動産収益を得る喜びを体験してみてください。その第一歩として、信頼性が高く透明性のあるとも宅をチェックしてみるのも良いでしょう。
▶トモタクの仕組みと投資の流れについてはこちらからご確認いただけます。